この記事では、

社会福祉士としてスキルアップしたいんだけど、何をしたらいいのか分からない
✅社会福祉士として自分の力量を高めたい!!
✅試験合格後の自己研鑽に悩んでいる…
という方に向けて
社会福祉士の私が実践していることをご紹介しています。
「社会福祉士としてのスキルアップに興味がある!」という方にとって参考になれば嬉しいです!
- 社会福祉士会に入会して研修を受けた
- 社会福祉士の行動規範を読み込んだ
- 書籍で知識を深めた

私の詳しいプロフィールはこちらです!
このプロフィールでは
✅社会福祉士を取得しようと思った理由
✅私の職歴
について述べています!
その1 社会福祉士会に入会して研修を受けた
私には、社会福祉士合格後にこんな悩みがありました。

「合格した後のスキルアップってどうしたらいいのだろう・・・」

「支援の現場で経験を積むだけでなく、専門的な研修を受けてみたい!!」
そんな時に、「社会福祉士会の入会の案内」が来ました。
私は、成年後見人の仕事に興味があり、
社会福祉士として後見人を受任するには研修を受ける必要があることも知り、
社会福祉士会に入会することにしました。
社会福祉士の試験に合格後に、社会福祉士会に入会します。まず、基礎研修Ⅰ、基礎研修II、基礎研修Ⅲで構成される基礎課程を修了する必要があります。そして、成年後見人人材育成研修、名簿登録研修を受けた後に名簿登録申請を行い、審査を受ける必要があります。
【解説】社会福祉士が基礎研修を受けて成年後見人を受任するまで
社会福祉士会に入会して感じたメリット
こちらの記事では、
「私が社会福祉会に入会して感じたメリット」について詳しく解説しています。
入会するかどうか悩んでいる方にとって参考になれば嬉しいです。
【社会福祉士会】入会して感じた3つのメリット
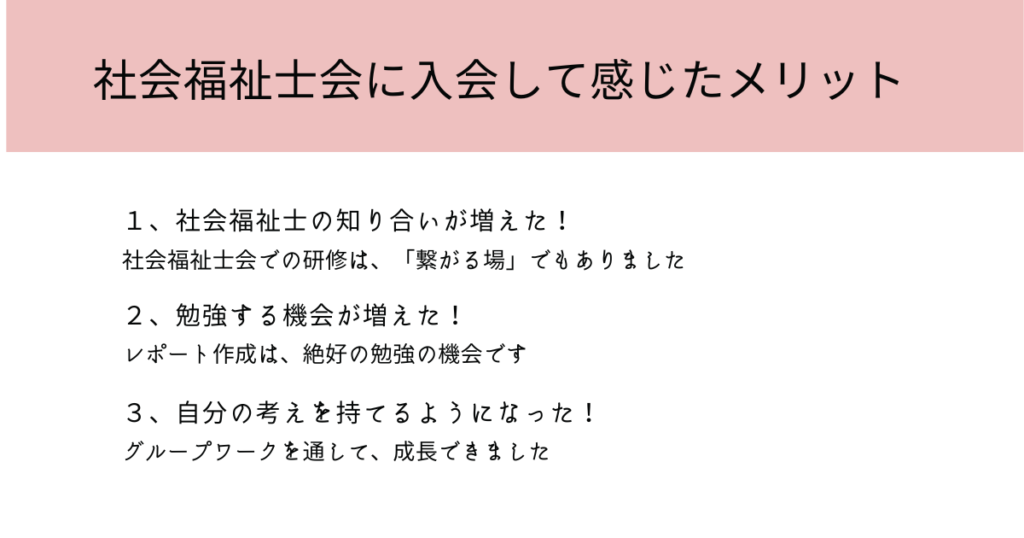
生涯学習制度とは?
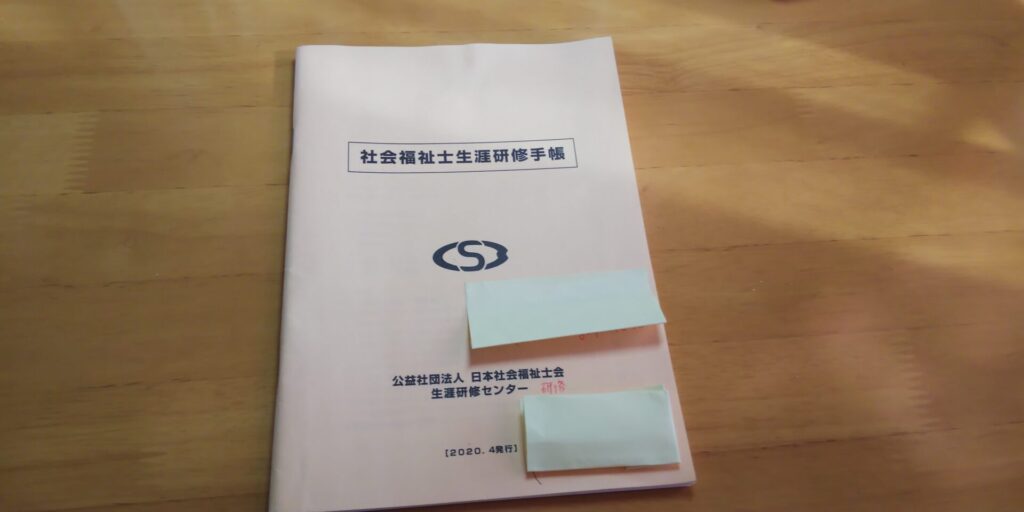
社会福祉士会には、「生涯学習制度」というものがあります。
生涯学習制度は、社会福祉士が自己研鑽していくために、
私は、とても心強い制度であると思います。
社会福祉士としてスキルアップをしたいと考えている社会福祉士の方に最適です。
生涯研修は、都道府県社会福祉士会に所属する会員(以下「会員」)が倫理綱領に基づいた相談援助活動が行えるように必要な知識、技術の専門性と倫理性を常に向上するさせるため生涯にわたって行う研修の総称であり、生涯研修制度は、今日の社会福祉の課題を解決するために、会員の自己研鑽の継続性を確保し、研修を通じて会員相互の連携を図ることによって、会員及び本会の力量を向上していくことを目的としています。
「社会福祉士生涯研修手帳」公益財団法人日本社会福祉士会 発行
生涯研修制度は、「基礎課程」と「専門課程」の二つの課程で構成されています。
基礎課程は、基礎研修Ⅰ、基礎研修II、基礎研修Ⅲで構成されています。
社会福祉士会に入会後、まずは「基礎研修I」を受講することにしました。
基礎課程のねらいとは?
基礎研修のねらいについて、
社会福祉士生涯学習手帳に以下のように書いてあります。
・社会福祉士として共通に必要な価値・知識・技術を学び、社会福祉士の専門性の基礎を身につける。
「社会福祉士生涯学習手帳」公益財団法人日本社会福祉士会 発行
スキルアップをして専門性を身につけたいと思っていた私にとって、
この基礎課程のねらいはまさにピッタリであると感じました。
社会福祉士のスキルに求められるスキルは多岐にわたります。
独学で自分で学んでいくよりも、
体系的にまとめらえたものを学んだ方がしっかりと身に付くと思い、
基礎研修を受講してみることにしました。
基礎研修Iを受講した
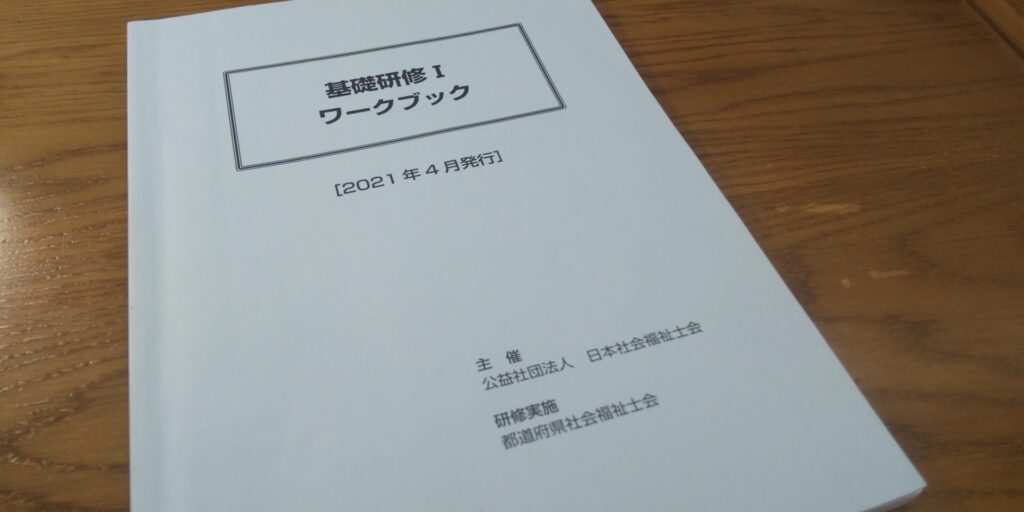
こちらの記事では、
基礎研修Iで学んだ内容について解説しています。
基礎研修Iを修了して得たスキル・経験について

基礎研修Iでは、ほぼ毎回グループワークがありました。
5、6人程のグループになり、話し合いをしていきます。
話し合いですので、当然個人の発言が求められます。
人見知りであり、緊張強いな私だったのですが、回数を重ねることで
発言に慣れることができました。
基礎研修Ⅰを受講したことで、
私は話し合いのスキルが上がったと思っています。(あくまで私個人の感想です)

発言するのは本当に緊張します。
グループワークについて
基礎研修で経験したグループワークについては、
こちらで詳しく解説しています。よかったらご覧ください。
【社会福祉士会の基礎研修】グループワークではどんなことをやるのか?解説します
基礎研修IIを受講した
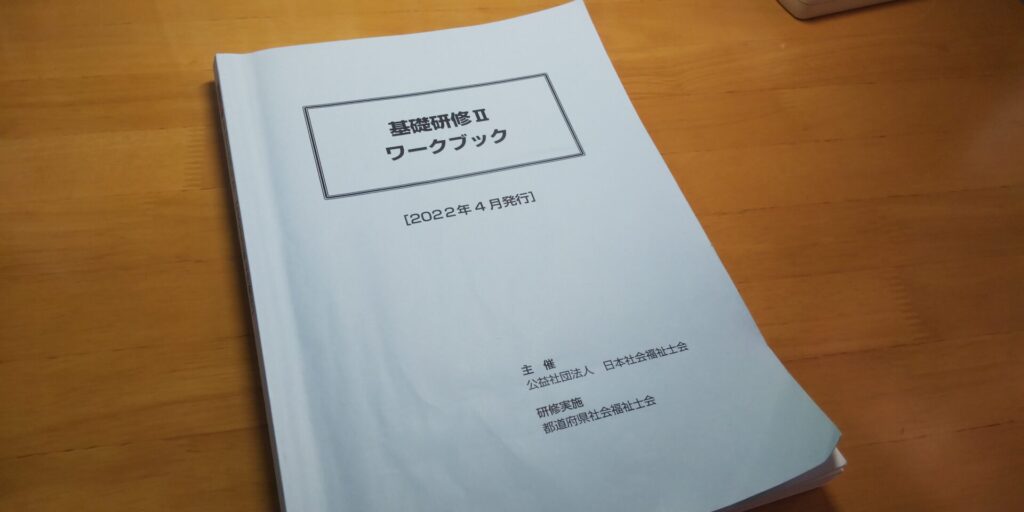
基礎研修Iを修了後、基礎研修IIを受講しました。
こちらの記事では、基礎研修IIで学んだ内容について詳しく解説しています。
基礎研修IIを修了して得たスキル・経験について

基礎研修IIの課題の一つに「社会調査を行う」というものがありました。
テーマを決め、そのテーマに沿った調査を行いました。
大学の卒業論文レベルとまではいきませんが、実際にアンケートをとり、
その結果をまとめて分析を行い、レポートに執筆しました。この課題は、非常にやりがいがありました。
以下のような、多様なスキルをフル活用したからです。
基礎研修IIを修了して得たスキル・経験について
- 調査テーマを考えるスキル
- 調査の方法を考えるスキル
- アンケートの構成を考えるスキル
- アンケートを知り合いにお願いするスキル
- アンケートを分析するスキル
大変ではありましたが、その分成長できたと思っています!!
その2 社会福祉士の行動規範を読み込んだ
日々の支援を経験や勘に頼るのではなく、
専門職としての支援を行うためには
どうしたらいいのか悩んだことはありませんか?

そんな時は、「社会福祉士の倫理綱領」と「社会福祉士の行動規範」が役に立ちます!
これらは、日々の支援に悩んだ時に参考になります。
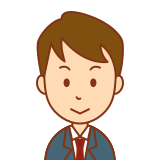
この支援でよかったのだろうか・・・

私の支援はブレてないかな・・・
と悩んだら、「社会福祉士の倫理綱領」を見てみると支援のヒントがあります。
例えば、こんな倫理綱領があります。
3. (受容) 社会福祉士は、自らの先入観や偏見を排し、クライエントをあるがままに受容する。
社会福祉士の倫理綱領 より
「クライエントに対する倫理責任」の一つなのですが、
クライエントとの関わり方において、参考となる指針ではないでしょうか。
自らの支援の拠り所とすることで、支援のレベルアップにつながると思います。
行動規範を現場で実践した
こちらの記事では、私が現場で経験し、実践してきた事をもとに、
行動規範について解説しました。よろしければご覧ください。
【社会福祉士の倫理綱領・行動規範】解説しました
その3 書籍で知識を深めた
書籍を読み知識を身につけて、
現場で実践していくことでスキルアップにつながります。
私が購入してきた現場で役立つ書籍をご紹介します。
社会福祉士の倫理綱領を現場で実践
仕事が始まる前のちょっとした隙間時間や休憩時間に、読み返しています。なんとなく支援をするのでなく、しっかりとした根拠をもとに支援をするためには、行動規範は不可欠であると思います。専門職として、レベルアップするためには日々のちょっとした積み重ねが大事ですよね。
月刊誌を読む

最新の情報を頭に入れておくのは大切であると思います。
福祉に関する法律は、頻繁に改正されており、
サービス内容に関わってくる場合もあります。
無理のない範囲で読んでおきたいですね。
私の職場では、幸いなことに数種類の月刊誌を取り寄せており、職員なら誰でも自由に読むことができます。「月刊福祉」「さぽーと」などの月刊専門誌です。自分で購読するとなるとお金もかかり、保管する場所も必要ですから、職場で無料で読めるのはとてもありがたいです。職場で活用できるものは、フル活用してスキルアップしちゃいましょう!!
まとめ
ここまでお読み頂きありがとうございます。
この記事では、社会福祉士の取得後に私が取り組んできた、
スキルアップの三つの方法について解説させて頂きました
- 社会福祉士会に入会して研修を受けた
- 社会福祉士の行動規範を読み込んだ
- 書籍で知識を深めた
専門職として活動していくには、常に知識と技術のブラッシュアップに
取り組んでいくことが必要であると思います。
働きながら研修を受けていくのは、時間とお金がかかり決して楽ではありません。
ですが、志を同じくする社会福祉士の横をつながりを作り、
お互いに励まし合いながら一緒に頑張っていきましょう!
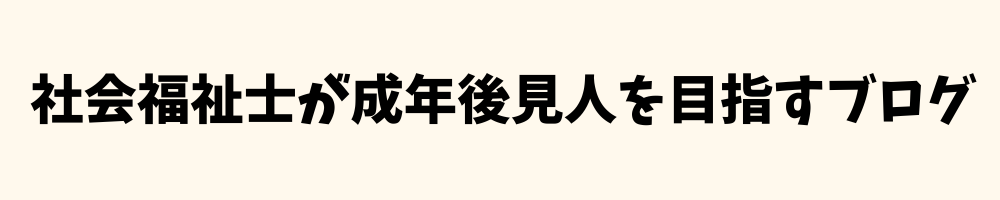
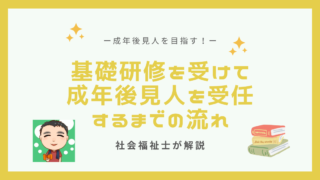
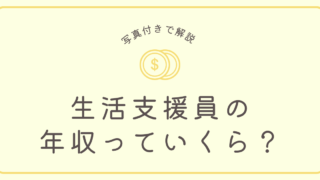
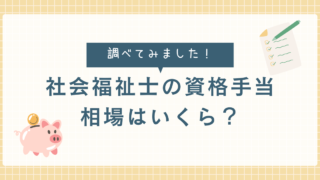
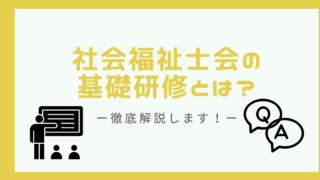
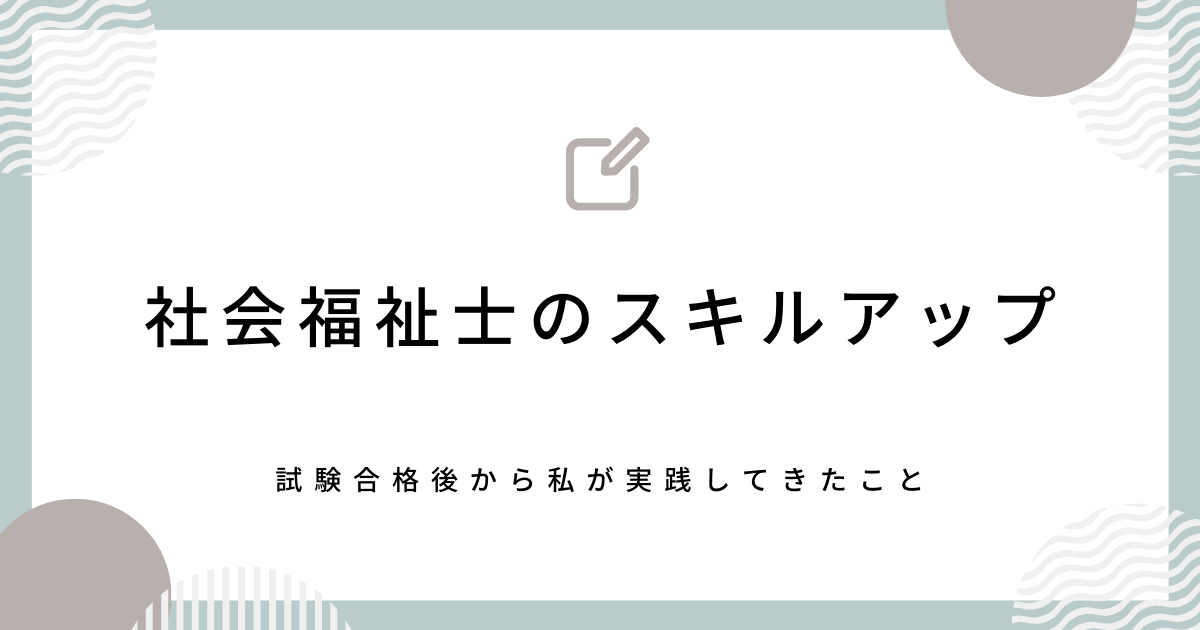
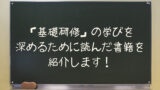
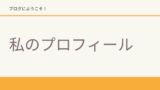
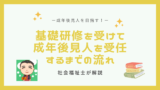


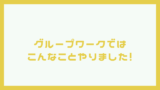




コメント