初めまして!「だいすけ」です!
このブログにお越し頂きありがとうございます!
・「社会福祉士と利用者の関係」について「社会福祉士の倫理綱領」や「社会福祉士の行動規範」を元に考察しています!

利用者さんとどんな関係性を気づいたらいいんだろう…
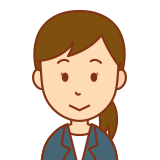
これから実習だけど利用者さんとの関係作りってイメージできないなぁ…
という方にとって参考になれば嬉しいです!

なぜ社会福祉士の倫理綱領をもとに考えるのか?
「社会福祉士の倫理綱領は社会福祉士の羅針盤」
とも言えるものであると思っています。
つまり、利用者さん支援の仕事をしていて.
・困った時や
・判断に悩んだ時に
「社会福祉士の倫理綱領」を頼りにすることで
解決へのヒントや支援の道筋が見えてくると思います。
社会福祉士の価値観が示されている
社会福祉士の倫理綱領には社会福祉士として持つべき価値観が示されており、
社会福祉士として様々な判断をする際に役立ちます
社会福祉士の倫理綱領を見ることで
「社会福祉士であるならば、こんな風に考えてみたらいいんだなぁ」
と判断の目安ができます
ゆえに、利用者さんとの関係作りにおいても参考になります
社会福祉士の行動規範
社会福祉士の行動規範は、
倫理綱領を行動レベルに具体化したものです
関係作りを実践していく上では、この行動規範が非常に参考になります
関係作りの参考になる倫理綱領
それでは
社会福祉士が利用者との関係作りにおいて
参考になる倫理綱領をみていきたいと思います。
倫理綱領では、「クライエント」という言葉が使われています。
ですので、利用者のことをクライエントと表現していきます。
倫理綱領
1.(クライエントとの関係)社会福祉士は、クライエントとの専門的援助関係を最も大切にし、それを自己の利益のために利用しない。
社会福祉士の倫理綱領
まず、「社会福祉士とクライエントとの関係」とは
そもそもどんなものであるのかについて考えてみたいと思います。
利用者と相談員という関係
具体的にイメージしやすくするために、
・社会福祉士→とある高齢者施設のデイサービスの相談員
・クライエント→デイサービスの利用者
として考えてみます。
「利用者が相談員に相談をする」という場面においては、
・相談員は利用者からデイサービスに関する相談を受けます
・利用者は相談員にデイサービスに関する相談をします
相談員は、社会福祉士という専門職という立場で相談を受けるわけです。
つまり、この相談員と利用者の関係は、
相談員が利用者が援助をするための関係であると言えます。
行動規範
行動規範とは、倫理綱領を具体的な行動レベルにしたものになります。
上記の倫理綱領には、「5つの行動規範」があります。
1−1
社会福祉士はクライエントに対して、相互の関係は専門的援助関係に基づくものであることを説明しなければならない。
社会福祉士の行動規範
この行動規範も以下のように、当てはめて考えてみたいと思います。
・社会福祉士→とある高齢者施設のデイサービスの相談員
・クライエント→デイサービスの利用者
この相談員と利用者の関係は、支援をするための関係であるということですね。
支援のための関係ですので、
・相談員が支援とは全く関係のないことを聞いたり、
・支援とは全く関係がないのに私的に自宅を訪問したり、
なんてことはあってはならないということです。
・援助をするための関係である
1−2
社会福祉士は、クライエントとの専門的援助関係を構築する際には、対応な協力関係を尊重しなければならない。
社会福祉士の行動規範
社会福祉士とクライエントの関係は、上司と部下のような上下関係ではありません。
対等であり、横並びの関係であるということです。
この行動規範も以下のように、当てはめて考えてみたいと思います。
・社会福祉士→とある高齢者施設のケアマネジャー
・クライエント→介護認定を受けた支援が必要な高齢者
ケアマネジャーは、高齢者にとって必要なサービスを調整して、
高齢者が困ることがないようにサポートしていきますよね。
介護保険のサービスについて、高齢者の方が詳しければ必要なサービスを
高齢者自身で決めていくこともできるかも知れません。
反対に、サービスに詳しくなければケアマネジャーが持つ知識や経験を頼りに
していくしかありません。
このような場合ですと、情報をもつケアマネジャーの立場の方がどうしても
優位であると感じてしまうかも知れません。
このように感じてしまうのは良くないということですね。
ケアマネジャーとの関係は対等であり、問題解決の主体はクライエントである
ということを認識しておくのが大切ですね。
1−3
社会福祉士は、専門職としてクライエントと社会通念上、不適切とみなされる関係をもってはならない。
社会福祉士の行動規範
「不適切な関係」とは具体的にどんな関係なのか。
ここでは、書籍を参考にみていきたいと思います。
社会福祉士がクライエントに対して友人や恋人に対するかのような感情(例えば好き、嫌い、苦手などの感情)を抱き、…以下略
三訂 社会福祉士の倫理 倫理綱領実践ガイドブック p55
性的な言動やストーカー行為と見なされるような言動を伴う関係
三訂 社会福祉士の倫理 倫理綱領実践ガイドブック p55
このような関係は、専門的援助関係であるとは到底言えないですよね。
自分は大丈夫と思わずに、このような関係になってしまう可能性があることを
頭に入れて私も業務に臨んでいきたいと思います。
1−4
社会福祉士は、自分の個人的。宗教的・政治的な動機や利益のために専門的援助関係を利用してはならない。
社会福祉士の行動規範
1−5
社会福祉士は、クライエントと利益相反関係になることが避けられないときは、クライエントにその事実を明らかにし、専門的援助関係を修了しなければならない。その場合は、クライエントを守る手段を講じ、新たな専門的援助関係の構築を支援しなければならない。
社会福祉士の行動規範
最後に
以上、
社会福祉士と利用者の関係について
「社会福祉士の倫理綱領」をもとに考えてみました。
社会福祉士の倫理綱領はこのように、
社会福祉士としての判断や行動していく上で非常に参考に
なるものであると思います。
日頃の実践で悩んだとき、倫理綱領を読み返してみることで
ヒントを得られる場合もあると思います。ぜひ参考になさってみてください!
記事作成時に参考にした書籍
最後までお読みいただきありがとうございました!
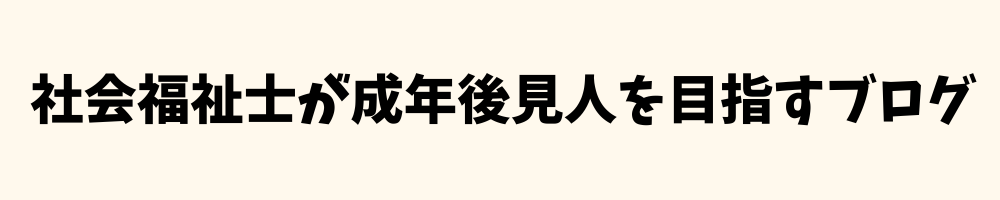
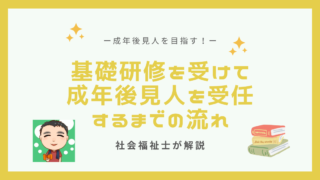
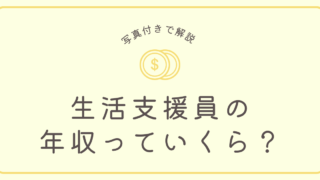
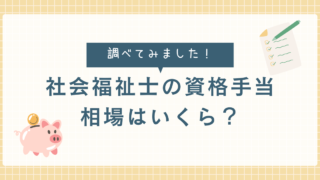
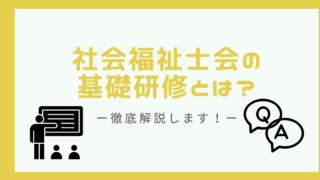
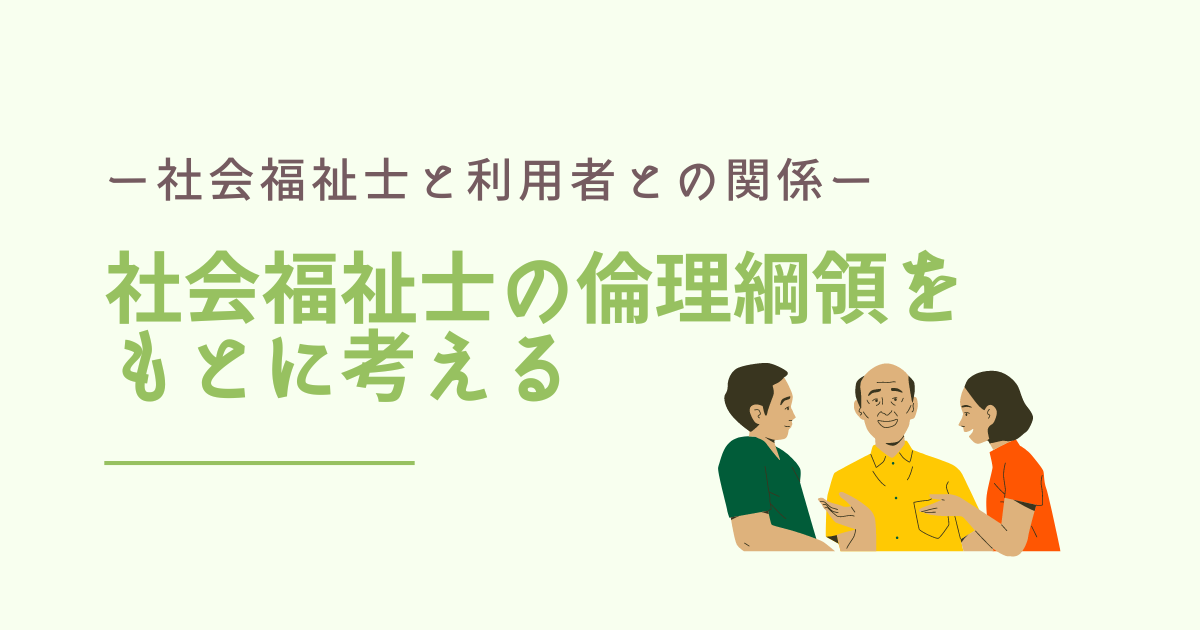
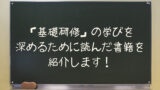

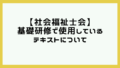
コメント