「利用者との関わり方ってどうしたらいいの?」
私は障害者施設の職員に転職するとき,、こんな不安を感じていました。
「どう接すれば利用者と信頼関係が築けるのか」と疑問や不安を感じている現役の障害者施設職員も多いと思います。
本記事では、現役の障害者施設職員が利用者との関わり方に悩む初心者職員向けに、具体的な工夫や支援のコツを解説しました!
利用者との関わり方を学ぶことで、信頼される職員として成長する一歩を踏み出していきましょう!

障害者施設での利用者との関わり方と

障害者施設で働くうえで、利用者との関わり方は支援の質を大きく左右します。
利用者はそれぞれ異なる特性や背景を持っており、
一律の対応では安心感や信頼関係を築くことが難しくなります。
そのため、まずは障害等の疾患で一括りでみるのではなく、利用者一人ひとりを理解する姿勢を持ち、尊重することが基本となります。
施設職員は、ただ支援を行うのではなく、利用者の生活の一部を共にする存在として寄り添う意識が大切となってきます。
こうした視点を持つことで、利用者にとっても過ごしやすい環境が生まれ、支援の効果も高まります。
なぜ「関わり方」が重要なのか?
障害者施設において職員と利用者の関わり方は、日常生活の質や安心感に直結します。利用者は支援を受けるだけでなく、人との関係を通じて自尊心や意欲を育むため、適切な関わりが欠かせません。
また、信頼関係が築かれることで、利用者は自分の思いを表現しやすくなり、自己決定や主体的な行動にもつながります。
逆に、不適切な対応が続けば不安や不信感を招き、支援効果が低下する恐れがあります。
そのため、職員は一方的に関わるのではなく、利用者の視点を大切にする姿勢が求められます。関わり方の工夫は、利用者の生活の安定と成長を支える大切な基盤となります。
・関わり方次第で利用者の安心感や信頼感が大きく変わる
・自立や社会参加の意欲につながる重要な要素
・不適切な関わり方は利用者の不安や萎縮を招く恐れがある
>> 利用者との関わり方が学べる書籍
職員が抱えやすい悩みと課題とは?
障害者施設で働く職員は、利用者との関わり方において多くの悩みを抱えやすいのが実情です。利用者一人ひとりの特性やニーズが異なるため、対応方法に迷いが生じることも少なくありません。
特に、行動や感情のコントロールが難しい場面では、適切な支援の仕方を模索することが大きな課題となります。
また、利用者の自己決定を尊重しながら安全を守るバランスにも苦労することがあります。さらに、家族や関係機関との連携の中で情報共有や調整が複雑になるケースもあります。
こうした悩みや課題に向き合うためには、職員同士の協力や専門的な知識の習得が欠かせません。
【現役職員が解説】障害者施設の職員が抱える悩みとは?よくある悩みとその解決策
・職場環境や働き方に関する悩み
・利用者への対応に関する悩み
・給与や待遇に関する悩み

職員が抱えやすい悩みについて下の記事で詳しく解説しています

利用者一人ひとりを理解するための基本姿勢について

障害者施設での支援は、利用者一人ひとりの特性を理解することから始まります。利用者は生活歴や障害の特性、得意不得意などが異なり、同じ対応では適切な支援につながりません。
そのため、日常の様子を丁寧に観察し、行動や表情から気持ちを汲み取る姿勢が必要です。また、本人の希望や意向を尊重することで、支援を受ける側の主体性が守られます。
さらに、職員間で情報を共有し合うことで、利用者にとって一貫性のある支援が実現します。理解を深める姿勢は、利用者が安心して施設で過ごせる環境づくりの基盤となります。
特性や好みを把握するための観察ポイント
利用者の特性や好みを把握するには、日々の行動や反応を丁寧に観察することが重要です。食事や活動の際にどのようなものを好むのか、表情や態度から読み取ることができます。
また、声のかけ方や支援の仕方によって利用者の反応が変わる点も大切な手がかりです。
さらに、苦手なことや不安を感じる場面を知ることで、無理のない支援計画を立てることが可能になります。観察を通じて得られた情報を積み重ねることで、利用者に合ったより良い関わり方が見えてきます。
>>障害者施設で働く前に読んでおきたい書籍

高齢者介護の現場から転職する際に購入した書籍です!
入門書にピッタリの内容なんです
・イラスト、写真が豊富で分かりやすい!
・事例が豊富でイメージがしやすい!
・隙間時間でも読みやすい!
>>これから生活支援員として働く方におすすめしたい本をご紹介!
記録や情報共有の工夫をしてみる
利用者への支援を継続的に充実させるためには、日々の記録と情報共有が欠かせません。観察した内容や利用者の変化を簡潔にまとめ、誰が見ても分かりやすい形で残すことが大切です。
また、記録は職員同士の共通理解を深める役割を果たし、支援の一貫性を保つ助けとなります。
さらに、家族や関係機関と共有できる形に整理することで、利用者を取り巻く支援体制がより強化されます。記録と情報共有を意識的に行うことで、利用者にとって安心できる支援環境が築かれます。
利用者と信頼関係を築くための関わり方について
障害者施設での支援において、信頼関係は円滑なコミュニケーションの基盤となります。利用者に安心感を与えるためには、職員が一貫した対応を心がけることが大切です。日々の声かけや接し方が安定していれば、利用者は安心して気持ちを表現できるようになります。
また、利用者の話を丁寧に聞き取り、否定せずに受け止める姿勢も信頼を築く要素です。
小さな約束を守ることや、気持ちに寄り添った行動を重ねることで、職員と利用者の関係はより深まっていきます。信頼関係は支援の効果を高める重要な土台となります。

下の記事では
「福祉専門職として目指すべき利用者との関係性」を考えてみました
>>どんな関係性を目指すべきか?【社会福祉士と利用者との関係】
傾聴と共感の姿勢を持つ
利用者との関わりでは、相手の話を丁寧に聞き取る傾聴の姿勢が重要です。言葉だけでなく、表情や仕草など非言語的なサインにも注意を向けることで、気持ちをより深く理解できます。
また、利用者の思いを否定せず「わかります」と共感を示すことで、安心感や信頼感が生まれます。共感の言葉を添えるだけでも、利用者は受け入れられたと感じ、自分の考えを表現しやすくなります。
傾聴と共感を心がけることは、利用者の自己肯定感を高め、前向きな関わりを築く基盤となります。
一貫した対応で安心感を与える
障害者施設での支援では、職員が一貫した対応を取ることが利用者の安心につながります。対応が日によって変わると、利用者は混乱や不安を抱きやすくなるため注意が必要です。同じ行動や声かけを続けることで、利用者は予測が立てやすくなり、落ち着いた生活を送りやすくなります。
また、職員間での支援方法に差があると不信感を招くこともあるため、情報を共有し統一した対応を心がけることが大切です。一貫性のある関わりは、利用者に安心をもたらし、信頼関係を築くための土台となります。
- 食事の場面
- 毎食前に「手を洗いましょう」と必ず声をかけ、全員が同じ順番で進める。ある職員だけが省略せず、どの職員も同じ流れを守る。
- 入浴の場面
- 入浴の順番を毎日変えず、掲示板や絵カードで示し、誰が支援しても同じ順序を伝える。
- 外出の場面
- 「外に出る前は必ず帽子をかぶる」と決めておき、職員によって声をかけたりかけなかったりしない。
- 余暇活動の場面
- DVD鑑賞や音楽活動のとき、開始前に「これから〇〇をします」と予告してから始める。突然始める職員がいたり、説明する職員がいたりと対応を変えない。
- 就寝準備の場面
- 就寝時間になったら毎日同じ声かけ(「そろそろ寝る時間ですよ」)を行い、照明を落とす流れを統一する。
自己決定を尊重する支援の工夫
障害者施設での支援では、利用者の自己決定を尊重する姿勢が欠かせません。本人に選択の機会を与えることは、自立心を育み、生活への意欲を高めることにつながります。
例えば、食事や活動内容を複数提示し、利用者自身が選べるようにすることが有効です。また、職員が先回りして決めるのではなく、利用者の希望を丁寧に聞き取る姿勢が大切です。
小さな選択を積み重ねることで、利用者は自分の意見を表現しやすくなり、主体的に生活に関わる力を伸ばしていけます。自己決定を尊重する支援は、安心できる関係づくりの基本となります。
選択肢を提示して本人に選んでもらう
利用者の自己決定を尊重するためには、複数の選択肢を示し、その中から本人に選んでもらう工夫が有効です。
選択肢があることで、自分の意思を表現しやすくなり、主体的に行動する機会が増えます。
例えば、食事のメニューや活動内容を2~3種類から選べるようにするだけでも効果的です。
また、言葉での理解が難しい場合には、写真や絵カードを使って視覚的に示すと分かりやすくなります。選択の機会を積み重ねることは、利用者の自信や生活意欲を高める支援につながります。

障害者施設で実践していることを記事にまとめました!
施設の食事では「三種類のふりかけ」の中から好みの味を利用者さんに選んでもらっています。
・「のりたま味」
・「たらこ味」
・「梅じそ味」
があります。
>>社会福祉士が行う意思決定支援について【6つの事例を解説】
小さな成功体験を積み重ねる
利用者の自己決定や自立を支えるためには、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。無理のない課題を設定し、達成できたことを一緒に喜ぶことで、自信や自己肯定感が高まります。
例えば、身の回りの簡単な作業や短時間の活動でも「できた」という実感が利用者の意欲につながります。
また、失敗を責めず挑戦を認める姿勢を持つことで、安心して新しいことに取り組める環境が生まれます。小さな成功の積み重ねは、利用者が前向きに生活を送るための基盤となります。
小さな成功体験とはこんなことです!
食事の準備:昼食前にスプーンをテーブルに並べることができた。

身支度:朝の更衣で自分でボタンを一つ留められた。

清掃活動:居室で机を拭く、ゴミを一つゴミ箱に捨てることができた。

行動や情緒の困りごとへの対応方法について
障害者施設では、利用者の行動や情緒の困りごとに適切に対応することが重要です。困難な行動が見られた際には、まず否定せずに受け止める姿勢が求められます。
利用者が安心して気持ちを表現できる環境を整えることが、問題行動の軽減につながります。また、職員だけで対応が難しい場合は、医療機関や専門職と連携することも大切です。
観察と記録を通じて、困りごとの背景やパターンを把握し、個別の支援計画に反映させることで、より効果的な支援が実現します。日々の関わりの中で、冷静かつ柔軟な対応を心がけましょう。
行動や情緒の困りごとの具体例
- 食事の場面
・食事が気に入らず、皿をひっくり返す。
・順番を待てずに他人の食事に手を伸ばしてしまう。 - 日課や活動の場面
・急な予定変更に強い不安を示し、参加を拒否する。
・作業が思うように進まず、大声を出して混乱する。 - 対人関係の場面
・職員の注意に対して怒って物を投げる。
・他の利用者の行動が気になり、過剰に干渉してトラブルになる。

上記のような問題行動の背景を学べる研修に参加したことがあります。
下の記事で詳しく解説しました!
否定せず受け止める姿勢
利用者の行動や発言を否定せずに受け止める姿勢は、信頼関係を築く基本です。感情や考えを認めることで、利用者は安心して自分の気持ちを表現できます。
また、否定的な反応は不安や抵抗感を生むことがあるため注意が必要です。職員は相手の話に耳を傾け、共感や理解を示すことで、安心感と自己肯定感を育むことができます。
困りごとへの対応は、まず受け止めることから始め、必要に応じて支援方法を調整する柔軟さが大切です。日々の積み重ねが、より良い関わりを生み出します。
専門的な対応が必要な場合の連携先
障害者施設で対応が難しい行動や情緒の問題が生じた場合は、専門的な支援機関との連携が重要です。医療機関や心理士、リハビリ専門職などと協力することで、利用者に適切な対応が提供できます。
また、関係機関との情報共有を通じて、支援の一貫性を保つことも可能です。必要に応じて福祉サービスや地域支援ネットワークを活用し、個別の支援計画に反映させることが大切です。
職員は、専門的知見を持つ機関との連携を積極的に行い、利用者の生活をより安全で安心なものにします。
分かりやすいコミュニケーションの工夫
障害者施設での支援では、分かりやすいコミュニケーションが利用者との円滑な関わりに欠かせません。
簡潔で具体的な言葉を使うことや、指示や説明を一度に詰め込みすぎない工夫が重要です。
また、言語だけでなく、身振りや絵カード、写真などの視覚的ツールを活用すると理解が深まります。
相手の反応を観察しながら、必要に応じて言い換えや補足を行う柔軟さも大切です。こうした工夫により、利用者が安心して行動や意思表示できる環境を整えることができます。

実習生さんに向けてに書いた記事です。
具体的で実践しやすいコツを解説させて頂きました!
やさしい言葉と具体的な表現を使ってみよう
利用者との関わりでは、やさしい言葉と具体的な表現を使うことが理解を助けます。抽象的な指示や難しい言葉は混乱を招くため、短く簡潔な言葉で伝えることが重要です。また、具体的な行動を示すことで、利用者が何をすればよいかを明確に理解できます。
例えば、「手を洗ってください」よりも「水道の蛇口をひねって手を洗いましょう」と具体的に伝える方が分かりやすくなります。
言葉を工夫することで、利用者の安心感や自信を高め、主体的な行動を促すことができます。
写真や絵カードなど視覚的ツールを活用してみよう
・視覚的ツールを活用すると理解が深まりやすい場合もある
・写真や絵カードは言葉で伝えにくい内容を直感的に理解しやすい
・活動の手順や日課を示す際に有効で、次の行動が把握しやすくなる

視覚的に理解しやすくする方法を考えてみましょう!
利用者への支援では、言葉だけでなく視覚的ツールを活用すると理解が深まります。
写真や絵カードは、言葉で伝えにくい内容を直感的に理解できる手段です。活動の手順や日課を示す際に使用すると、利用者は次に何をすればよいかを把握しやすくなります。
また、視覚的な情報は記憶の補助にもなり、不安や混乱の軽減にもつながります。ツールを活用する際は、利用者の特性に合わせて簡潔で分かりやすいものを選ぶことが大切です。こうした工夫により、安心して主体的に行動できる環境が整います。
職員として成長するためにできることとは?
障害者施設で働く職員が成長するためには、日々の経験を振り返り学ぶ姿勢が重要です。利用者との関わりで気づいたことや課題を記録し、改善策を考えることで支援力が向上します。
また、研修や勉強会に参加して専門知識や技術を継続的に学ぶことも大切です。さらに、先輩職員や同僚と情報交換を行うことで、多様な視点や支援の工夫を取り入れることができます。こうした取り組みを積み重ねることで、職員はより質の高い支援を提供できるようになり、利用者にとって安心で信頼できる存在となります。
研修や勉強会で支援技術を学ぶ
職員が質の高い支援を提供するためには、研修や勉強会への参加が有効です。最新の支援技術や知識を学ぶことで、利用者に合わせた柔軟な対応が可能になります。
また、研修では他施設の事例や専門職の経験を共有できるため、自分の支援方法を見直すきっかけにもなります。
学んだ内容を職場で実践し、フィードバックを受けることで、より効果的な関わり方を習得できます。
継続的な学びを通じて、職員は専門性を高め、安心で信頼される支援者として成長することができます。
>>【強度行動障害支援者養成研修】グループワークで経験したこと

現場で働く職員さんは
受けておくべき研修であると感じました!
事例検討や振り返りで実践力を高める
職員が支援力を向上させるためには、事例検討や振り返りが有効です。日々の関わりで生じた課題や対応を共有し、改善点を話し合うことで、次の支援に活かせる知見を得られます。
また、成功事例や失敗事例を分析することで、利用者の特性に応じた柔軟な対応力が身につきます。
振り返りの過程で、職員自身の支援の強みや改善点に気づき、実践力を体系的に高めることが可能です。
こうした継続的な取り組みが、安心で質の高い支援提供につながります。
まとめ|利用者に寄り添う関わり方を身につけよう
障害者施設での支援では、利用者一人ひとりに寄り添う関わり方が重要です。特性や希望を理解し、自己決定や安心感を尊重することで、信頼関係を築けます。
また、分かりやすい言葉や視覚的ツールの活用、行動や情緒の困りごとへの適切な対応も不可欠です。
職員自身は研修や事例検討を通じて支援力を高め、継続的に学び続ける姿勢が求められます。
日々の積み重ねが、利用者が安心して生活できる環境づくりにつながります。
関連記事
>>これから生活支援員として働く方におすすめしたい本をご紹介!
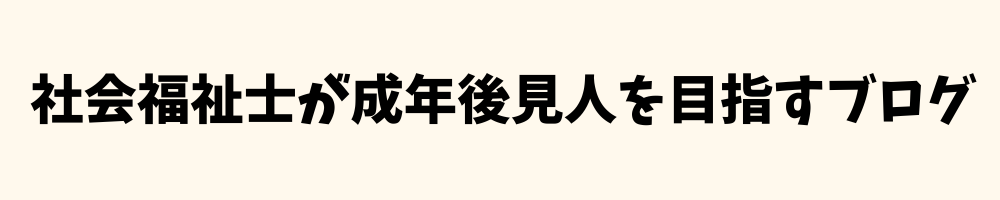
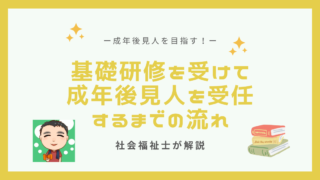
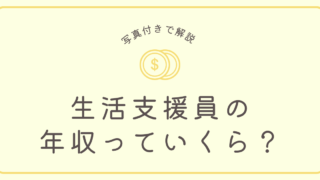
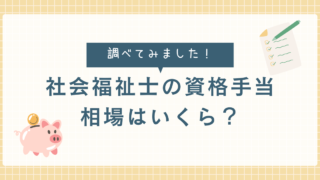
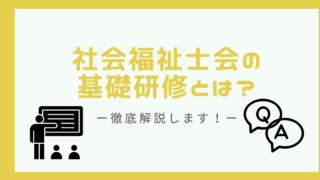
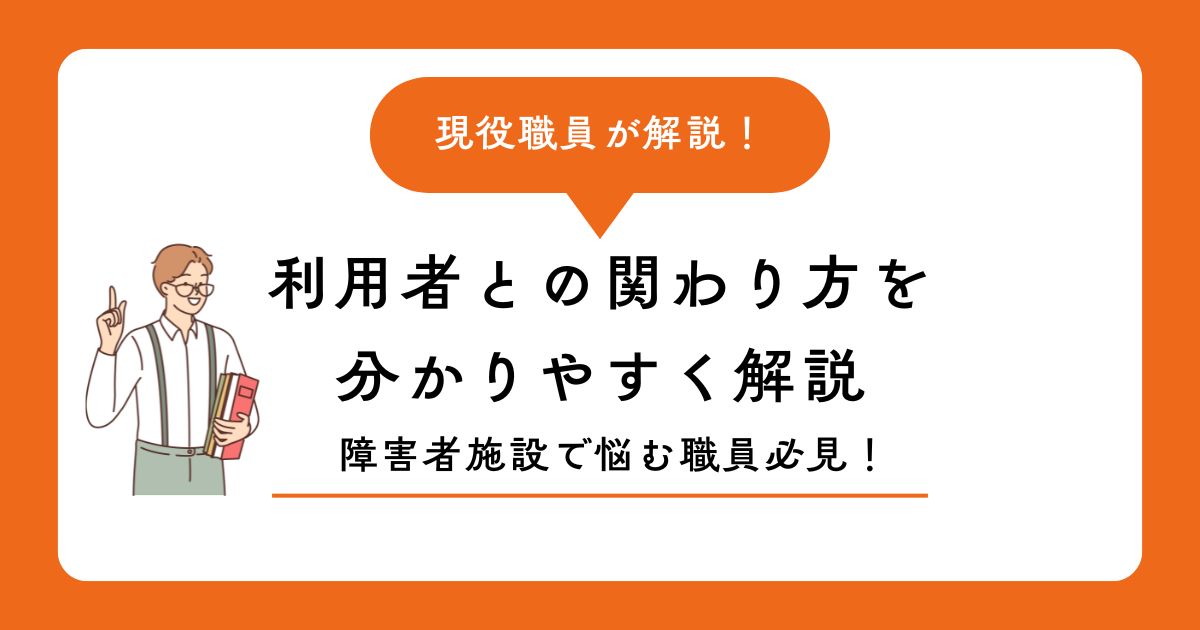
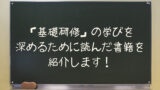


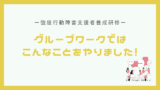



コメント