この記事で解説していること
この記事では、
福祉の世界におけるアドボカシーの具体例について解説しています

アドボカシーの具体例を知りたいぁ
という方にとって参考になれば嬉しいです!

だいすけ
1. アドボカシーの意味とは?
アドボカシー(Advocacy)とは、権利擁護のことを指し、社会的に弱い立場にある人々の声を代弁し、権利を守る活動です。
福祉の現場では、高齢者、障害者、子ども、生活困窮者、などの利用者が想定されます
アドボカシーが求められる場面の例
- 障害のある人が合理的配慮を受けられない場合
- 高齢者が虐待や詐欺の被害に遭っている場合
- 子どもが適切な教育や支援を受けられない場合
- 生活困窮者が必要な福祉制度を利用できない場合
社会福祉士にとってのアドボカシー
社会福祉士が支援を行うクライエントは、上記のような立場が弱い方が多く、
自ら声を上げることができない場合が多くあります。
社会福祉士は、そのような方々の声に耳を傾け、行動を起こし支援をしていく必要があります。
社会福祉士にとって、権利擁護は重要な責務の一つであると言えます。
「社会福祉士の倫理綱領」に明文化されており、日々の活動においてしっかりと意識したいところです
社会福祉士の倫理綱領より
社会福祉士は、クライエントの権利を擁護し、その権利の行使を促進する。
社会福祉士の倫理綱領
リンク
2. 福祉分野ごとの具体的なアドボカシー事例を解説
① 障害福祉のアドボカシー事例
- 合理的配慮を求める支援
ある企業で発達障害のある従業員が適切な配慮を受けられずに困っていました。支援者が企業と交渉し、作業環境の調整や業務内容の明確化を行うことで、当事者が働きやすくなりました。 - 障害者差別解消法を活用した訴え
公共交通機関のバリアフリーが不十分であることを訴え、自治体と交渉してエレベーター設置を実現。 - 成年後見制度を活用した財産管理支援
知的障害のある方が詐欺の被害に遭うリスクがあったため、成年後見制度を利用し、金銭管理のサポートを実施。
・参考文献
「聴覚障害児のセルフアドボカシー指導と合理的配慮について」
② 高齢福祉のアドボカシー事例
- 高齢者の虐待防止活動
介護施設での身体拘束が問題視され、第三者機関が調査を行い、介護の質の向上を図る。 - 医療・介護サービスの適正利用を支援
不要な入院や施設入所を防ぐため、地域包括支援センターが本人の希望に沿ったケアプランを提案。 - 消費者被害から守る取り組み
高齢者が悪質商法に騙されるケースが増加。地域の福祉相談員が定期的に見守り、トラブルを未然に防ぐ。
③ 児童福祉のアドボカシー事例
- 児童虐待を防ぐための支援
スクールソーシャルワーカーが学校と連携し、虐待が疑われる児童を保護。 - 特別支援教育を受ける権利の擁護
発達障害のある児童が適切な教育を受けられるよう、学校との交渉を行い、個別支援計画を策定。 - 里親制度の普及・支援活動
児童養護施設で育つ子どもたちが家庭で暮らせるよう、里親制度の普及を進める。
④ 生活困窮者支援のアドボカシー事例
- 生活保護申請の同行支援
窓口で申請を拒否されたケースで、支援者が同行し、適切な手続きをサポート。 - 住宅確保要配慮者への支援
ホームレス状態の人が住まいを得るため、地域の福祉団体が住宅確保支援を実施。 - 就労支援と社会復帰サポート
職業訓練や就労支援プログラムを活用し、生活困窮者が安定した収入を得られるよう支援。
3. アドボカシーを実践するためにできること
- 利用者の声をしっかり聴く
- 必要な制度や法律を学び、適切な支援を行う
- 福祉専門職(相談支援員、弁護士、行政職員)との連携を強化する
参考書籍
リンク
4. まとめ
福祉の現場では、アドボカシーが重要な役割を果たします。
支援者が適切に権利擁護を行うことで、利用者が安心して生活できる社会を実現できます。
支援の現場でできることを考え、実践していきましょう!
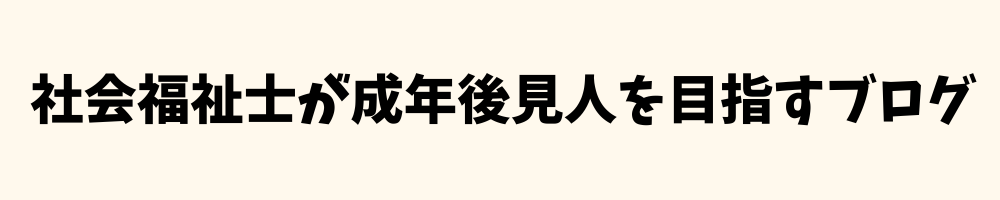
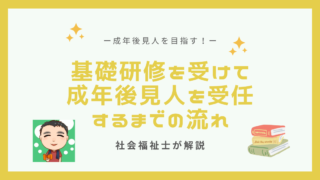
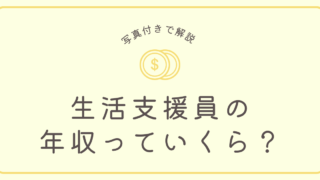
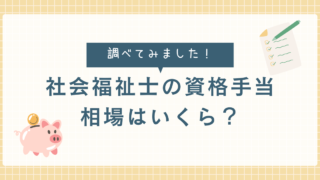
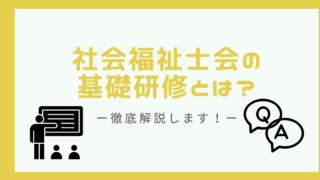
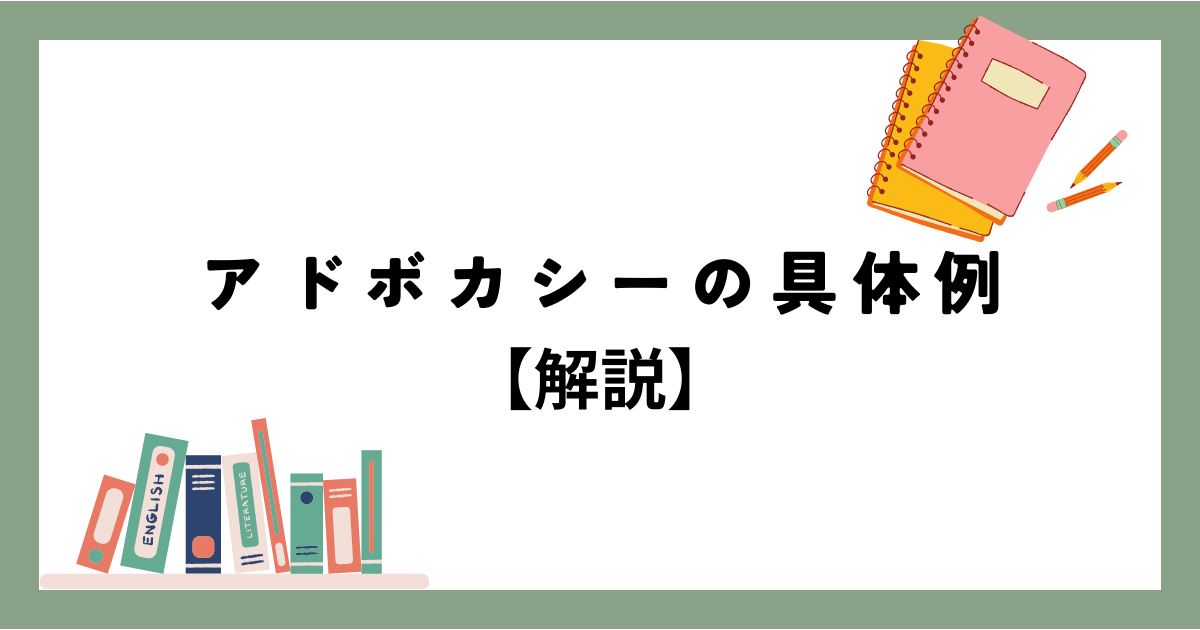
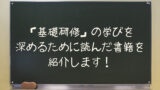


コメント