・「成年後見人材育成研修」ってどんなものか知りたい!
・「基礎研修Ⅰ」「基礎研修Ⅱ」「基礎研修Ⅲ」修了
・「成年後見人材育成研修」受講中(2024年度)
※この記事の情報は2024年6月時点の情報に基づきます。
※研修の日程や事前課題等は、
各都道府県社会福祉士会によって違いがあると思いますので、ご注意願います。

成年後見人材育成研修の日程
成年後見人材育成研修は、
日本社会福祉士会によって、研修カリキュラムが定められています。
全4日間のプログラムとなっています。私が受講した日程は以下のとおりです。
全て土曜日になっており、平日仕事の方でも参加しやすいようになっていました。
私は、シフト制の仕事のため希望休を取った上で研修に参加しています!
| 日程 | 日付 |
|---|---|
| 1日目 | 2024年7月13日(土) |
| 2日目 | 2024年8月24日(土) |
| 3日目 | 2024年10月5日(土) |
| 4日目 | 2024年11月9日(土) |
研修カリキュラムの詳しい内容について
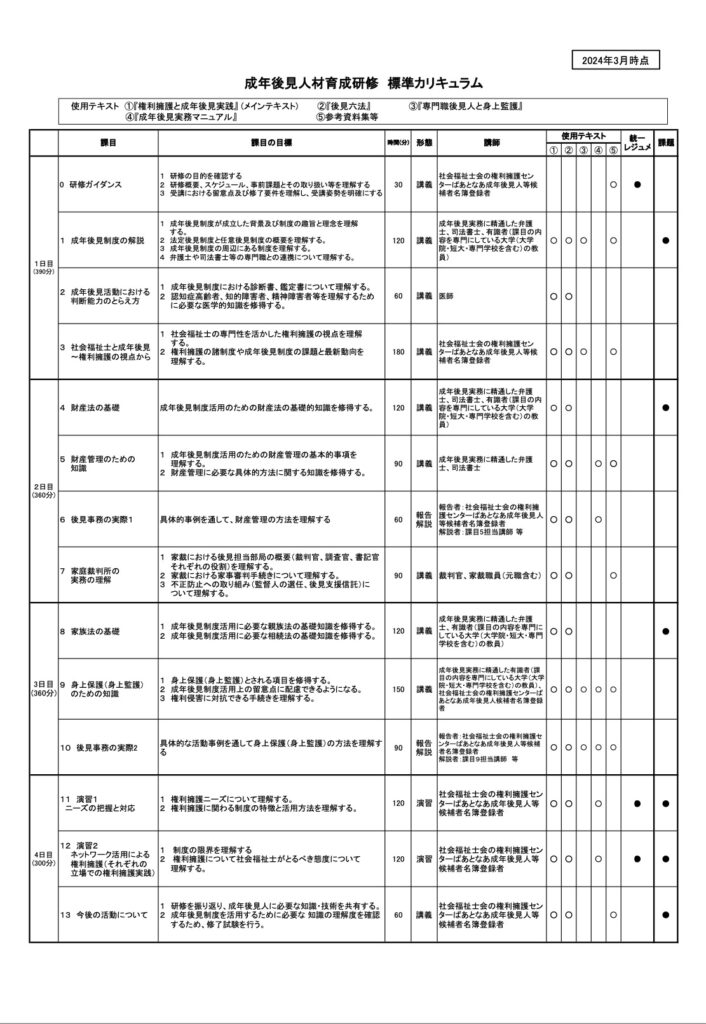
研修プログラムの詳しい内容は、
公益財団法人日本社会福祉士会生涯研修センターのホームページで確認できます。
・参考ページ「成年後見人養成研修について」
・URL https://www.jacsw.or.jp/ShogaiCenter/kenshu/2023-0323-1738-22.html
事前課題 1回目
研修1日目までに提出する必要のある「事前課題」は二つありました。
その1
社会福祉士として成年後見等を務めるにあたり、踏まえるべき視点について
この課題に取り組むにあたり、まず成年後見制度の基本理念を参考にしました
- 自己決定の尊重
- 本人の現有能力の活用
- ノーマライゼーション
そして、具体例を挙げる必要があることから、
「施設で暮らす知的障害のある利用者さんが施設を出たい」という意思を表明したと
仮定し、基本理念を参考にして視点を考察しました
その2
・成年後見制度における任意後見制度の意義について
・法定後見制度と異なる点について
法定後見と任意後見の異なる点について、
以下の観点で文章をまとめました
- 後見人の選定方法について
- 本人への介入時期について
- 後見事務の内容について
- 後見人に付与される取消権について
研修1日目
学んだ科目について
- 成年後見活動における判断能力の捉え方
- 成年後見制度の解説
- 社会福祉士と成年後見ー権利擁護の視点から
・「成年後見における判断能力の捉え方」について
この科目では、現役の医師の方が講師として講義をしてくださいました。
内容は上記の通りです。
実際に使用している診断書を参考に、現場の医師の先生がどのように考え、診断をしているのかリアルな話が聞けました。
先生の経験談・事例を数多く話してくださり、
「現場ではこんなことがあるんだなー」と興味深い内容ばかりでした。
・参考ページ「成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引」について
・URL https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_02/index.html
事前課題 2回目
・成年後見人の財産管理事務とはどのようなものか
・財産管理事務としてどのようなことをする必要があるか
まず、財産管理事務の説明を簡単にまとめました
続いて、テキストを参考に
財産管理事務の内容を箇条書きでまとめました
- 財産の引き継ぎ
- 金融機関への届出
- 財産調査
- 財産目録の作成
- 収支予定表の提出
・被後見人の居住用不動産を管理する際の留意事項について
・居住用不動産を処分する際の手続きについて
研修2日目
学んだ科目について
- 財産法の基礎
- 財産管理のための知識
- 後見事務の実際1
- 家庭裁判所の実務の理解
事前課題 3回目
・成年後見人の身上配慮義務に関する民法の規定についても
・成年後見人の職務範囲に含まれていない事項について
・利益相反とはどのようなことか
・利益相反行為がなぜ禁止されるのかについて
・利益相反の具体例を3つ挙げて説明
研修3日目
学んだ科目について
- 家族法の基礎
- 身上監護のための知識
- 後見事務の実際2
事前課題4回目
・研修修了後に成年後見制度をどのように活用するか
・成年後見活動に関わる意義について
研修4日目
学んだ科目について
- 演習1 ニーズの把握と対応
- 演習2 ネットワーク活用による権利擁護
- 今後の活動について
成年後見人材育成研修で使用したテキストについて
研修で使用するテキストは、
指定されたものを個人で購入する形でした
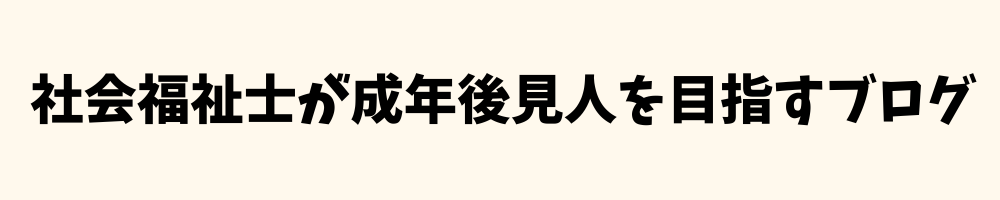
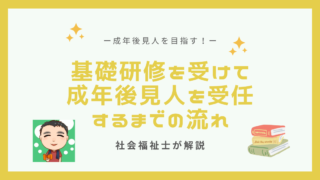
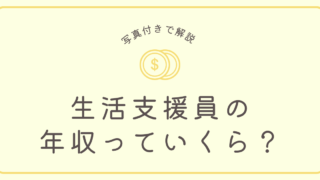
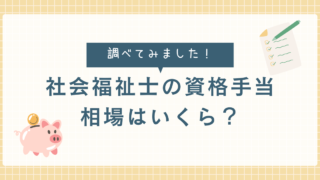
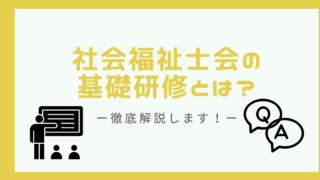
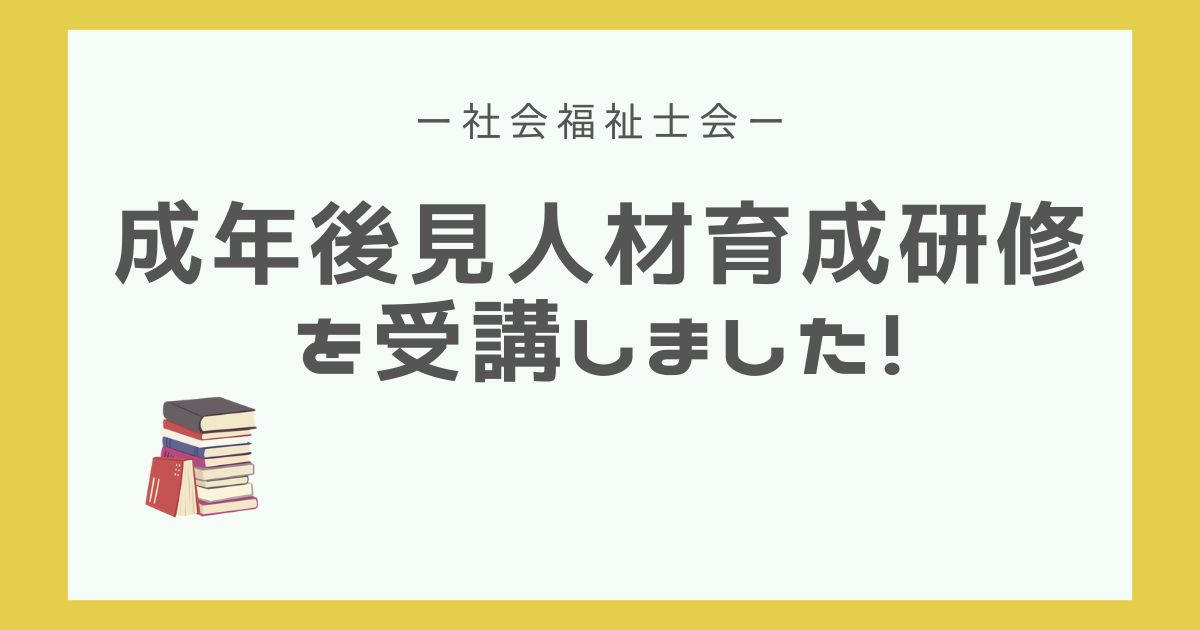
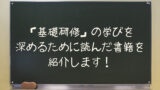
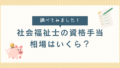
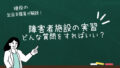
コメント