障害者施設での実習を控え、
「レクリエーションはどうすればいいんだろう?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか?
初めての現場では、「利用者との関わり方」や「レクの進行の仕方」等にわからないことだらけで戸惑うこともありますよね。
この記事では、障害者施設の実習で役立つレクリエーションのアイデアや
注意点を初心者向けに解説しました。
実際のレク事例や進行のコツや役立つ書籍もご紹介しています。
実習前の不安を安心に変えるヒントをぜひ見つけてください!

>【実習生向け】障害者施設の実習に役立つ記事をまとめました!
1. 実習でレクリエーションを行う意味とは?
障害者施設での実習では、レクリエーションが大きな役割を果たします。
レクを通じて利用者の心身の活性化やコミュニケーション促進が期待されます。
また、実習生自身が利用者との関わり方を学ぶ機会にもなります。
活動の中で信頼関係を築けると、実習全体の充実度も高まります。
レクは特別なスキルがなくても始めやすく、実習評価にもつながります。
目的や対象者を意識して取り組み、より意義ある実習にしていきましょう!
1-1. 障害者施設でのレクの役割

障害者施設でのレクリエーションには、生活に彩りを加える役割があります。
身体や認知機能の維持・向上を目的とした活動としても重要です。
利用者同士や職員との交流を促し、孤立感の軽減にもつながります。
また、楽しみや達成感を通じて、自己表現や自己肯定感を育む場にもなります。
日常生活の一環として、無理なく参加できることが大切であり、
個々の障害特性や体調に配慮した企画であることが求められます。
1-2. 実習生に求められるレクの目的とは
| 目的 | ポイント | 解説 |
|---|---|---|
| 観察力を育成する | 利用者の反応を観察・記録する | レクリエーション中の表情や動き、言葉などを観察し、支援に活かすために記録を取る力が養われます。 |
| 心構えを学ぶ | 寄り添う姿勢が大切 | 大きな盛り上がりよりも、一人ひとりのペースに合わせ、丁寧に関わることが大切です。 |
| より良い実践に繋げる | ふりかえりと記録に活かす | レクリエーションの内容や利用者の様子を記録し、支援や自身の学びに活かせるようにしましょう。 |
実習生が行うレクリエーションには、「学び」と「実践」の両方の目的があります。
利用者と関わりながら、障害理解や支援の工夫を体験的に学び、活動を通じて、利用者の反応を観察し記録する力も養うことも狙いです。
また、実習後のふりかえりや記録も大切な学びとなります。
1-3. 利用者との信頼関係づくりにも効果的
レクリエーションは、利用者と実習生の距離を縮めるきっかけになります。
一緒に楽しむことで、自然な会話や笑顔が生まれやすくなります。
形式ばらない交流は、信頼関係の土台を築く第一歩となります。
利用者のペースに合わせた関わりは、安心感を与える要素にもなります。
実習生の姿勢や声かけひとつで、関係性は大きく変わっていきます。
信頼関係の構築は、レク後の支援場面にも良い影響を与えます。
>障害者施設におけるレクリエーションの目的とは?事例も紹介します
2. レクリエーションを企画する前に知っておきたいこと
実習でレクリエーションを行う前には、事前準備がとても大切です。
利用者の障害特性や体調、興味関心などを事前に把握しましょう。
実習先の施設方針や支援方針に合った内容を選ぶことも重要です。
そして何より安全面に十分に配慮し、無理のない活動を心がけることが求められます。
また、時間配分や役割分担も事前に確認しておき現場での実施を想定し、
柔軟に対応できる準備を整えましょう。
2-1. 利用者の障害特性を理解する
レクリエーションを企画する際は、「利用者の障害特性」を理解することが重要です。
・見通しが持ちにくく、急な変更が不安につながる
・複数の指示を同時に理解することが難しい
・刺激の強い環境(大きな音・人が多い環境)で落ち着きにくくなることがある
身体的・知的・精神的な特性に応じた配慮が求められます。
一人ひとりの特性に合わせた内容であれば、参加意欲も高まります。
無理なく参加できる工夫が、安心感や楽しさにつながります。
特性に合わない活動は、戸惑いや不安を招く原因となることもあります。
実習前に現場の職員に確認し、適切な配慮を反映した企画を心がけましょう。
>>障害特性について理解を深めたい方はこちらの記事が参考になります
「これから生活支援員として働く方におすすめしたい本をご紹介!」
2-2. 実習先のルールや方針を確認する
レクリエーションを企画する前に、実習先のルールや方針を確認しましょう。
施設ごとに支援の方針やレクの位置づけには違いがあります。
活動時間や利用できるスペース、必要な手続きなども事前に把握が必要です。
食べ物の持ち込みや感染症対策など、細かな制限がある場合もあります。
職員への事前相談を通じて、無理のない計画を立てることが大切です。
施設の方針に沿った企画は、実習生としての信頼にもつながります。
2-3. 「安全第一」の視点を忘れずに

レクリエーションを企画するうえで、最も大切なのは「安全第一」の視点です。
活動中の転倒や衝突、誤飲などのリスクを事前に想定しておきましょう。
障害特性によって注意すべきポイントは異なりますので個別の配慮が必要です。
活動場所の安全確認や道具の取り扱いにも十分注意を払いましょう。
万が一のために、職員と連携しながら対応方法を共有しておくことも大切です。
安全な環境づくりは、利用者の安心と楽しさを支える基本となります。
行事を企画する際のポイントとは?
3. 実習中におすすめのレクリエーションアイデアをご紹介!
実習中に行うレクリエーションは、簡単で安全に楽しめるものが理想です。
特別な準備がなくても取り組める内容なら、実習生でも実施しやすくなります。
歌や体操、ゲームなどは多くの施設で親しまれている定番の活動です。
人数や障害の程度に応じてアレンジできるものを選ぶのがポイントです。
利用者とのやりとりを大切にし、無理のないペースで進めましょう。
小さな成功体験や笑顔を引き出せるレクが、実習の充実につながります。
3-1. 準備が簡単!道具いらずのレク
実習中に取り入れやすいのが、準備が簡単で道具がいらないレクリエーションです。
手遊びやリズム体操、しりとりなどはその場で気軽に始められます。
道具が不要な分、片付けや移動の手間が少なく、安全面にも配慮できます。
参加者の表情や反応を見ながら、柔軟に内容を変えられるのも魅力です。
誰でも参加しやすく、利用者との距離も縮めやすい活動になります。
実習生にとっても負担が少なく、進行の練習にも適しています。
3-2. 誰でも参加しやすい体を動かすレク

体を動かすレクリエーションは、利用者の健康維持や気分転換に効果的です。
イスに座ったままでもできる体操やリズム運動なら、誰でも参加しやすくなります。
無理のない動きで、体をほぐしながら楽しめる内容を選ぶことが大切です。
音楽に合わせて手足を動かすと、自然と笑顔が生まれやすくなります。
活動後の「気持ちよかった」という声は、実習の成果にもつながります。
事前に職員と相談し、安全に配慮した運動を取り入れましょう
3-3. 会話が弾む!コミュニケーション重視のレク
コミュニケーションを重視したレクリエーションは、実習中に特におすすめです。
自己紹介ゲームや質問リレーなどは、自然な会話のきっかけになります。
話す・聞くといった双方向のやりとりが、信頼関係の構築につながります。
言葉が難しい方には、表情やジェスチャーでのやりとりも大切です。
会話を通じて利用者の興味や個性を知る貴重な機会にもなります。
無理に話を引き出すのではなく、安心して話せる雰囲気を心がけましょう。
3-4. 季節感を楽しめるレクリエーション例

| 季節 | レクリエーション例 | ねらい・効果 |
|---|---|---|
| 春 | お花見ごっこ、桜の工作 | 季節を感じる、視覚や手先を使った創作活動 |
| 夏 | うちわ作り、盆踊り | 涼を感じる工夫、伝統文化の体験 |
| 秋 | 紅葉の塗り絵、秋の味覚クイズ | 色彩認識や記憶の活性化、会話のきっかけ作り |
| 冬 | クリスマス会、年賀状づくり | 年中行事を楽しむ、集中力や創造力の促進 |
季節感を取り入れたレクリエーションは、利用者にとって大きな楽しみになります。
春はお花見ごっこや桜の工作、夏はうちわ作りや盆踊りが人気です。
秋は紅葉をテーマにした塗り絵、冬はクリスマス会や年賀状づくりも喜ばれます。
季節の行事を取り入れることで、日々の変化を感じやすくなります。
五感を刺激するようなレクは、記憶や感情にも良い影響を与えます。
準備や進行は無理のない範囲で工夫し、参加しやすい形にアレンジしましょう。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 季節の変化を感じやすくなる | 行事や自然のテーマを取り入れることで、利用者にとって日常の変化が明確になる |
| 五感への刺激が得られる | 見て・触れて・聞いて楽しむ活動が、脳への良い刺激に |
| 準備・進行は無理のない範囲で工夫 | 実習生は無理せず、できる範囲で工夫し、安全に配慮して実施 |
3-5. 個別対応にも使えるアレンジ方法
個別対応を意識したレクリエーションは、多様な障害特性に配慮するうえで重要です。
同じレクでも、進行スピードや声かけの方法を工夫することで対応が可能です。
例えば、難しい動作は省略したり、選択肢を視覚化するなどの調整が効果的です。
個々の興味や得意なことを取り入れることで、参加意欲が高まります。
無理に全員同じことをさせる必要はなく、柔軟なアレンジが求められます。
一人ひとりに寄り添った対応が、安心感や信頼関係の構築につながります。
4. レクリエーションの進行で気をつけたいポイント
レクリエーションの進行では、「わかりやすさ」を意識することが大切です。
まずは「活動の目的」や「流れ」を、簡潔にゆっくり伝えることが基本です。
参加者の表情や反応を見ながら、無理なく進行するよう心がけましょう。
進行中は肯定的な声かけを行い、不安や戸惑いを軽減する工夫も必要です。
予想外の反応があっても慌てず、柔軟に対応する姿勢が信頼感につながります。
事前の準備と進行中の配慮が、レクリエーション成功のカギです。
4-1. 声かけのコツとトーンの工夫
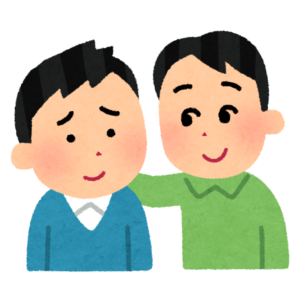
声かけは、利用者との信頼関係を築くうえで非常に重要な要素です。
明るくゆっくりとしたトーンで話すことで、安心感を与えられます。
言葉はできるだけ具体的にし、曖昧な表現は避けるようにしましょう。
「がんばって」よりも「〇〇ができてすごいね」と伝えるのが効果的です。
声の大きさは相手の反応を見ながら調整し、威圧感を与えない工夫も必要です。
肯定的な言葉がけを意識することで、参加意欲の向上にもつながります。
4-2. 集団をまとめる進行テクニック
集団でのレクリエーション進行には、事前準備と段取りが欠かせません。
参加者全体に視線を配り、誰かが取り残されないよう配慮が必要です。
開始前には活動の内容や目的を、短くわかりやすく説明しましょう。
進行中は個々の反応に合わせて声かけやテンポを調整します。
状況に応じて休憩や変更を入れる柔軟さも、円滑な進行には重要です。
緊張せず笑顔で取り組む姿勢が、自然と集団の雰囲気を和らげます。
5. 実習記録に活かせるレクのふりかえり方法
実習で行ったレクリエーションは、振り返りを通じて学びを深めることが大切です。
うまくいった点や利用者の反応を具体的に記録するようにしましょう。
反対に、戸惑った場面や改善点も率直に書き留めておくと次に活かせます。
「なぜその活動を選んだのか」「どう工夫したか」も記述に加えると説得力が増します。
記録は単なる報告ではなく、自分の成長を見直す貴重な材料になります。
ふりかえりを通して、実習記録に意味と深みを持たせることができます。
5-1. 何を記録すればよいか?基本の視点

実習記録では、「事実」「気づき」「次への改善点」の3点を押さえることが基本です。
まずは、実施したレクリエーションの内容や参加人数を具体的に記録しましょう。
次に、利用者の反応や雰囲気、自分自身の行動や声かけも振り返ります。
うまくいった理由や、うまくいかなかった要因も整理しておくと深い学びになります。
最後に、「次回どう工夫したいか」という視点を持つことで、記録が成長に変わります。

レポートの書き方を学んでおくと実習がスムーズになります!
>>『介護実習の記録・レポートの書き方』(Amazonで見る)
5-2. 「利用者の反応」を丁寧に振り返ろう
実習記録では、利用者の反応を丁寧に観察し、具体的に書き留めることが重要です。
「笑顔」や「拍手」といった「表情」や「しぐさ」は、レクの効果を示す大切な手がかりになります。
声のトーン、発言の内容、集中度なども記録すると支援の質向上につながります。
反応が薄い場合も、その理由や状況を考察することで学びが深まります。
「楽しそうだった」だけで終わらず、どの場面でそう感じたかまで振り返りましょう。
一人ひとりの変化や気づきに目を向ける姿勢が、実習生としての成長を支えます。
5-3. 職員からのフィードバックを活かす
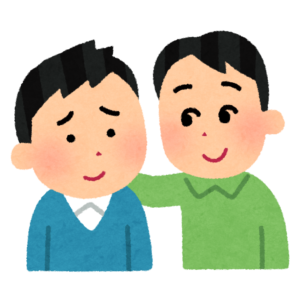
職員からのフィードバックは、実習をより深く学ぶための貴重なヒントになります。
良かった点は素直に受け止め、今後の自信や行動につなげましょう。
改善点は防衛的にならず、なぜ指摘されたかを丁寧に考えることが大切です。
「指摘=失敗」ではなく、「成長のきっかけ」と捉える視点が求められます。
実習記録には、職員の助言と自分の受け止めを書いておくと振り返りに役立ちます。
現場ならではの視点を学び、自身の支援力に反映させていきましょう。
6. 実習前の不安を減らすためにできる準備
実習前の不安を減らすには、事前準備を丁寧に行うことが大切です。
まずは実習先の施設情報や支援内容を確認し、現場のイメージを持ちましょう。
次に、よく使われる用語や障害特性に関する基本的な知識を整理しておくと安心です。
レクリエーションの例や進行方法を動画や書籍で学ぶのも効果的です。
事前に簡単な声かけの練習をしておけば、実際の場面で落ち着いて対応できます。
準備が整っているという自信が、不安をやわらげ、実習を前向きに進める力になります。
6-1. 参考になる動画や書籍をチェック
実習前に参考になる動画や書籍を確認することは学びを深めるうえで重要です。
活動の雰囲気を掴むのに役立ちます。
書籍では、宮本晋一氏の『楽しい すぐ使える 福祉レクリエーション』が、実践的なレク種目を多数紹介していて便利です。
『事例を通して学びを深める施設実習ガイド』(2025年4月刊)
には、実習生が直面する実例をもとにした具体的な指導が掲載されています。
これらを事前にチェックすることで、
レクリエーション企画の幅が広がり、不安の軽減にもつながります。
6-2. シミュレーションやリハーサルも効果的
レクリエーション実施前にシミュレーションやリハーサルを行うことは非常に有効です。
実際の流れを想定して動くことで、手順や声かけの不安を軽減できます。
友人や家族に協力してもらい、実際に試してみると課題が見つかりやすくなります。
タイムスケジュールや参加者の動きを確認することで、本番に余裕が生まれます。
予測できない場面も想定しておくと、当日のトラブルにも柔軟に対応できます。
準備と練習を重ねておくことで、利用者にとって安心できるレクが実現できます。
6-3. 無理せず「できることから」始める姿勢を大切に
実習では、すべてを完璧にこなそうとせず「できることから」始める姿勢が大切です。
無理に大がかりなレクを行おうとせず、小さな活動から着実に経験を積みましょう。
例えば、歌やあいさつなどの簡単な関わりも立派な支援になります。
できたことをしっかり振り返ることで、次への自信につながります。
利用者や職員の反応を見ながら調整していく柔軟さも実習では求められます。
自分のペースで取り組むことで、継続的な成長と実習の充実感が得られます。
7. まとめ|実習のレクは「工夫」より「安心感」が大切
実習でのレクリエーションは、特別な工夫よりも「安心感」が大切です。
利用者が落ち着いて参加できる雰囲気づくりを第一に考えましょう。
難しいことに挑戦するより、できることを一緒に楽しむ姿勢が求められます。
実習生自身が緊張せずに関わることで、利用者にも安心が伝わります。
安全への配慮や相手に寄り添う気持ちが、信頼関係の土台となります。
「誰かの役に立ちたい」という思いを形にする第一歩が、実習のレクです。
7-1. 利用者の笑顔を引き出すレクとは
利用者の笑顔を引き出すレクリエーションには、無理のない参加が欠かせません。
得意なことや関心のある分野を取り入れると、自然と表情が明るくなります。
声かけのトーンやテンポを工夫し、安心して楽しめる雰囲気づくりも大切です。
また、勝ち負けよりも過程を楽しめる活動は、心のゆとりを生み出します。
「できた」「楽しかった」という感情が、笑顔につながる大きな要素です。
7-2. 実習生としての姿勢が一番の評価ポイント
実習で評価されるのは、スキルよりも基本的な姿勢や態度です。
あいさつや報告・連絡・相談を丁寧に行うことが信頼につながります。
積極的に学ぼうとする姿勢は、職員から高く評価されやすい要素です。
困った時に無理をせず相談することも、大切な実習生の資質といえます。
日々の関わりの中で「真摯な態度」を持ち続けることが最も重要です。
障害者施設実習・完全攻略ロードマップ
実習を成功させるために、あわせて読んでおきたい記事をステップ順にまとめました!
今のあなたに必要なステージをチェックしてみてください!
【STEP 1:実習に行く前の準備】
【STEP 2:実習中の振る舞いと記録】
- 障害者施設での実習に臨む抱負と心構えについて
- 【障害者施設の実習】「質問」に関する疑問を解説!
【STEP 3:実習をきれいに締めくくる】
【STEP4:実習後にやること】
最後までお読みいただきありがとうございました!
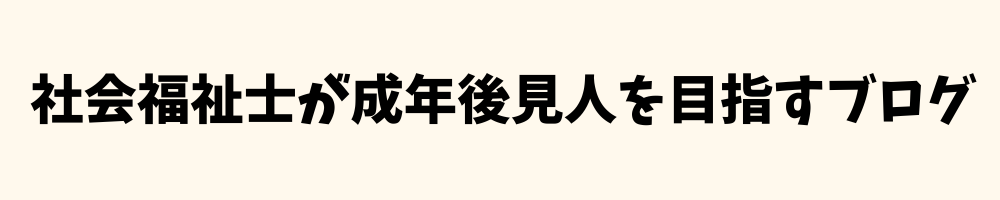
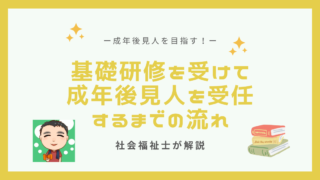
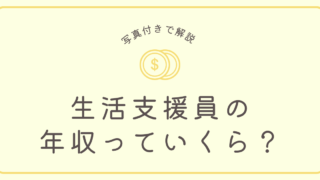
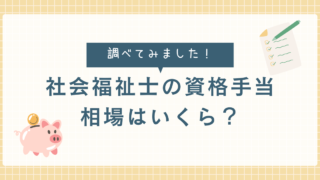
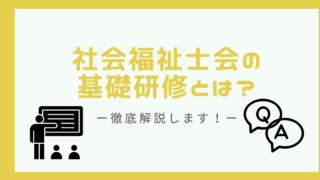
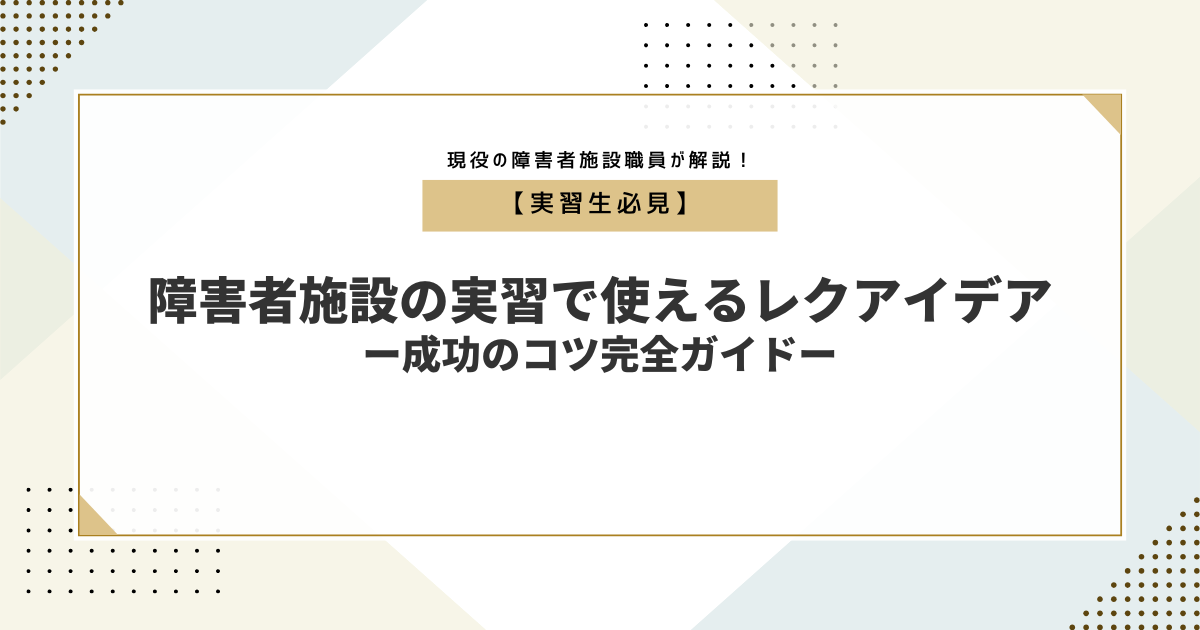
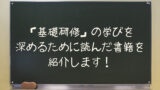
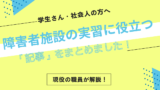
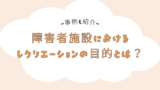


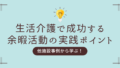
コメント