・障害者施設の人間関係のリアルな実態について
・人間関係が良い職場の特徴について
・ストレスを減らし円滑に働くためのコツついて

障害者施設の人間関係って大変そう…

職員同士のトラブルはある?働きやすい職場はどこ?
こんな不安を抱えていませんか?
障害者施設の現場は、職員同士の協力が重要です
なぜなら、職員でチームを組んで支援をする必要があるからです
利用者さんの支援は一人だけでは決してできません
職員同士の協力が必要な場面が多くあり、それゆえに人間関係に悩む人もいます。
本記事では、
「障害者施設 人間関係」と検索された方にとって有益な情報を提供できるよう
障害者施設職員の経験を活かして記事を書いています。

1. 障害者施設の人間関係のリアルとは?
障害者施設における人間関係は、主に「三つ」に分けることができます。
- 職員同士の人間関係
- 職員と利用者との人間関係
- 職員と利用者の家族との人間関係
それぞれ詳しく解説します。
職員同士の人間関係について
障害者施設における職員同士の人間関係の特徴とは?
- チームワークが求められる
- 年齢層が幅広い
- 役職による関係性がある
- OJTの影響が大きい
チームワークが求められる

支援員以外にはどんな職種の人と連携するの?

看護師や相談員、リハビリスタッフなど、多職種と協力して支援を行います。
障害者支援は一人で完結する仕事ではなく、
先輩、同僚、後輩と協力して支援を行う必要があります。
また、多職種(支援員・看護師・相談員など)との連携も不可欠となってきます。
年齢層が幅広い
現場では、20代の若手から60代のベテランまで、
幅広い年齢層の職員が働いていることが多くあります。
世代の違いにより、価値観の違いや指導方法のギャップが生じやすい可能性があります。
また、自分より年上の人が後から入職してくる場合も多くあります。
その方に仕事を教える場面などコミュニケーションと取る時に気を遣うこともあります。
役職による関係性がある
施設長や主任などの管理職と現場職員の関係性が職場環境に影響を与えます。
この関係性が良好で風通しの良い職場 では当然、働きやすい雰囲気があります。
しかし、管理職と現場の関係性が悪く、トップダウンが強い職場では意見が通りにくいため、
現場の職員が常に不満を口にしている職場もあります。
OJTの影響が大きい
新人はベテラン職員をはじめ、
中堅(入職して3〜5年程度)の職員から直接指導を受けることが多いと思います。
障害者施設の仕事は、
実際に自分で行なって覚えていくということがほとんどだと思います。
最初の時や不明な点が生じた場合は、先輩職員がそばで指導をしてくれると思います。
指導の方法は、人によって大きく異なります。
教え方が厳しい職員と優しい職員の差が激しいケースがあり、
厳しい職員だった場合は、「わからないことが聞きづらい」と思うケースもあります。
障害者施設の現状がわかる一冊
障害者施設における職員同士の人間関係の課題とは?
- 人手不足による職員の負担増
- 派閥ができやすい
- コミュニケーション不足がストレスの原因に
- プライベートの関係が職場に影響を与える場合もある
- 離職率が高い職場は人間関係が変わりやすい
人手不足による職員の負担増
慢性的な人手不足の施設も多くあります。
そのため、一人当たりので業務量が多く、余裕がない職員がイライラしてしまうことがあります。
職員と利用者との人間関係について
障害者施設では、職員と利用者の関係性も非常に重要です。
支援の質だけでなく、日々の安心感や信頼関係にも直結します。
◎基本は「信頼関係の構築」
- 利用者のペースや特性を尊重する姿勢が大切
- 毎日の挨拶や会話、ちょっとした声かけが信頼につながる
- 支援の押しつけにならないように注意が必要
◎関わり方に悩むことも
- 感情のコントロールが難しい利用者への対応
- 職員によって接し方が違うことで、利用者が混乱することも
- 自立支援と過保護のバランスに悩む場面もある
◎良い関係を築くコツ
- 利用者の「できること」を見つけて伸ばす
- 言葉だけでなく、表情や態度でも安心感を伝える
- 職員同士で利用者への関わり方を共有し、チームで支援する意識を持
職員と利用者の家族との人間関係について
利用者本人だけでなく、その家族との関係も支援を行う上で欠かせないポイントです。
信頼される職員であるために、丁寧な対応と誠実なコミュニケーションが求められます。
◎家族との関係の重要性
- 家族は利用者の生活歴や特性をよく知る「情報源」
- 連携が取れていないと、支援がチグハグになりやすい
- 利用者の安心感にもつながるため、信頼関係は不可欠
◎よくある関わりの場面
- 送迎時や電話での連絡
- モニタリングや支援計画の説明
- 行事や面会などでの対面コミュニケーション
◎人間関係で悩みやすいところ
- 家族の要望と本人の希望が食い違うことがある
- 施設への不満や不信感をぶつけられることも
- 支援内容への「口出し」がプレッシャーになる場合も
◎良好な関係を築くには
- 丁寧な説明と、こまめな報告・連絡・相談(いわゆる「報連相」)を心がける
- 家族の思いに共感を示しつつ、専門職としての視点もきちんと伝える
- 感謝やねぎらいの言葉を忘れずに
2. 人間関係が良い障害者施設の見極め方
障害者施設で働くうえで、人間関係は職場の満足度を大きく左右します。
転職や就職の際には、事前にその雰囲気を見極めることが重要です。ここでは、見学や面接時にチェックしたいポイントを紹介します。
◎見学・面接時にチェックすべきポイント
- 職員同士の会話が明るく、活発に交わされているか
→ 挨拶が自然に交わされている職場は、風通しの良さを感じられます。 - 職員の表情や雰囲気が明るいかどうか
→ 無言で作業していたり、ピリピリした空気がある場合は注意が必要です。 - 職員が利用者に対して丁寧に接しているか
→ 利用者への対応は、そのまま職員間の関係性にも通じます。
◎求人票やホームページのチェックポイント
- 職場の写真に笑顔があるか、雰囲気が伝わるか
→ 実際の職場風景や行事の様子が掲載されていれば、参考になります。 - 離職率や勤続年数が書かれているか
→ 長く働いている職員が多い職場は、人間関係が安定している可能性が高いです。 - 「チームワークを大切にしています」「職員の声を反映」などの記載
→ 求人情報にもヒントが隠れています。
◎口コミ・評判も参考にしましょう
- 転職サイトやGoogleマップ、SNSの口コミもチェック
- 元職員や現役職員の声に耳を傾けることで、内部の雰囲気をある程度把握できます
3. 職場の人間関係を良好に保つコツ
障害者施設で働くうえで、利用者との関わりと同じくらい大切なのが、職員同士の関係性。良好な人間関係を築くことで、業務がスムーズになり、ストレスも軽減されます。ここでは、日々の業務のなかで意識したいポイントを紹介します。
◎基本は「挨拶」と「感謝」
- 明るい挨拶は良い関係の第一歩
→ 朝の「おはようございます」から、日常の雰囲気が作られます。 - 「ありがとう」を言葉にする習慣を持つ
→ 些細なことでも感謝を伝えることで、相手の気持ちも前向きになります。
◎相手の立場に立って考える
- 役割や立場による視点の違いを理解する
→ 支援員、看護師、調理員など、立場によって見えているものが違うことを意識。 - 相手を責める前に、自分の伝え方を見直す
→「どう伝えれば伝わるか」を考える習慣が、トラブル防止につながります。
◎雑談・ちょっとした会話も大切に
- 業務外のコミュニケーションが信頼関係を育む
→ 無理に仲良くなる必要はありませんが、共通の話題があると関係がほぐれます。 - 「共感」や「うなずき」を意識する
→ 話を聞いてもらえた、という実感が信頼感を生みます。
◎困ったときは早めに相談する
- 1人で抱え込まず、信頼できる上司や先輩に相談を
→ 我慢しすぎると関係がこじれる原因に。早めの行動が自分を守ります。
4. まとめ
障害者施設の人間関係で失敗しないために
障害者施設で働くうえで、人間関係は避けて通れない重要なテーマです。
職員同士の関係性、利用者やその家族との距離感など、関わる人の数だけ気遣いが求められます。
しかし、それは決して「大変なこと」ばかりではありません。
- 挨拶・感謝・共感を大切にすることで、信頼は少しずつ築かれていきます。
- 相手を理解しようとする姿勢が、人間関係をスムーズにするカギになります。
- 施設全体の雰囲気は、職員だけでなく利用者の安心にもつながります。
もし今、人間関係に悩んでいるなら、
それはあなたが「よりよい支援」を目指している証拠です。
無理をせず、相談できる相手を持ち、少しずつ関係を育てていきましょう。
「人を支える仕事」は、まず自分自身を大切にすることから始まります。
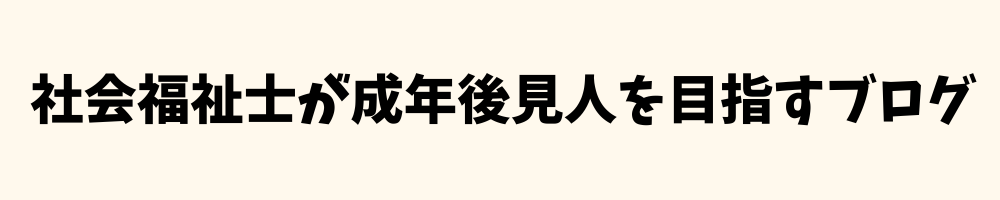
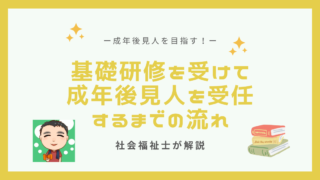
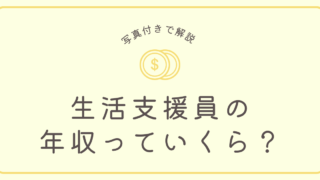
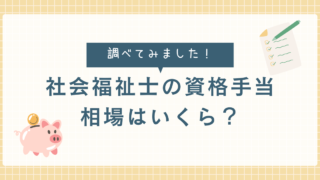
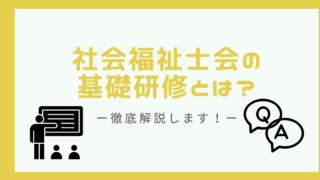
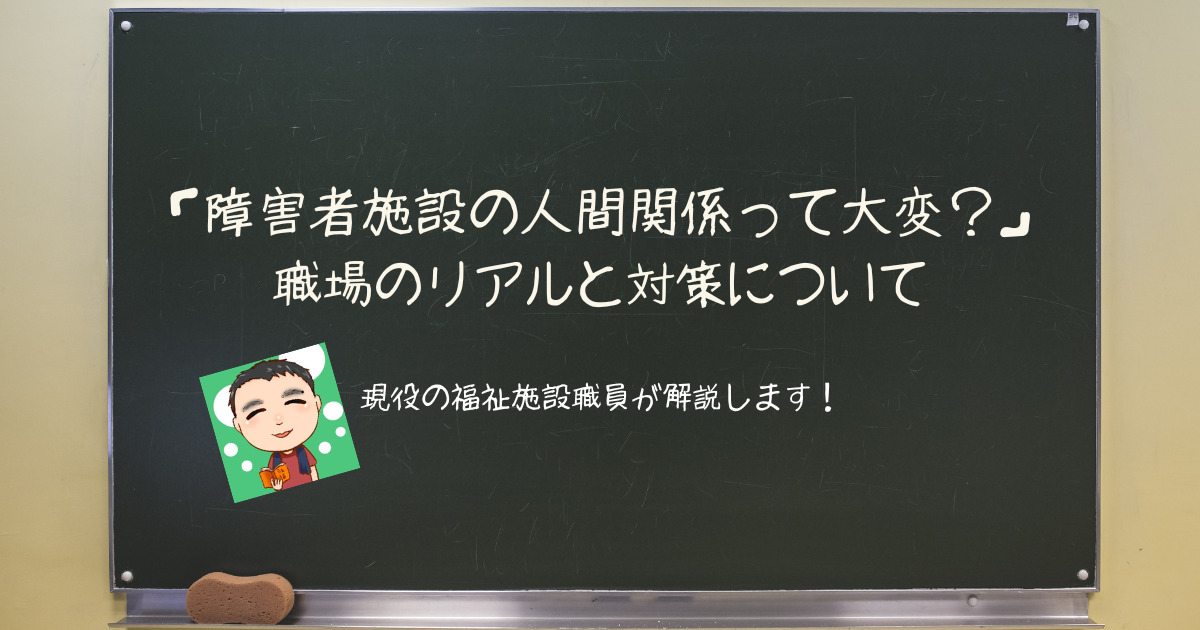
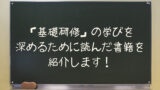

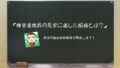
コメント